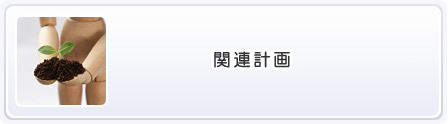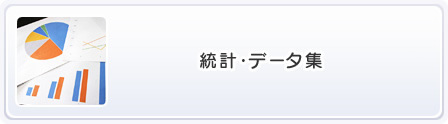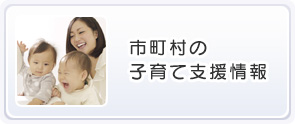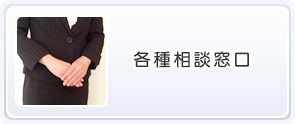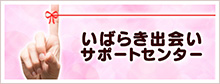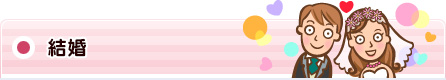
「出会い」の機会の提供と「縁結び」のために行われている取り組みをご紹介します。
- パートナーを探したい
- 結婚を支援したい
- いばらき結婚・子育てわくわくキャンペーン
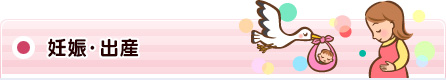
子どもが欲しい方向けや、妊娠されたばかりの方向けの情報をまとめました。
- 健康教育について
- 子どもが欲しい
- 妊婦さんになったら
- 出産後の支援
- 受胎調節実地指導員の指定等について
- 旧優生保護法への対応について
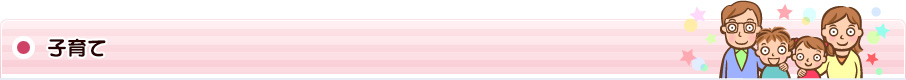
仕事と子育てを両立させるための取り組み、子どもとの生活に関する取り組み、子育て支援の取り組みに関する制度や情報をご紹介します。
- 子どもを預ける
- 放課後子ども対策について
- 子どもと一緒に集う
- 子育てサポート
- ひとり親家族への支援
- 子育て支援に取り組む
- 子どもの健康
- 子どもを守る
-
(一社)いばらき出会いサポートセンターのいばらき出会いサポートセンターPR業務委託に関するプロポーザルについて
-
(一社)いばらき出会いサポートセンターがいばらき出会いサポートセンターPR業務委託に関する企画提案を募集します。
-
令和7年度保育従事者処遇等実態調査事業業務委託に関するプロポーザルについて
-
令和7年度保育従事者処遇等実態調査事業業務委託に関する企画提案を募集します。
-
令和7年度認可外保育施設事故防止研修業務委託に関するプロポーザルについて
-
令和7年度認可外保育施設事故防止研修業務委託に関する企画提案を募集します。
-
令和7年度茨城県保育士等キャリアアップ研修事業業務委託に関するプロポーザルについて
-
令和7年度茨城県保育士等キャリアアップ研修事業業務委託に関する企画提案を募集します。
-
令和7年度子育て人材確保強化推進事業業務委託に関するプロポーザルについて
-
令和7年度子育て人材確保強化推進事業業務委託に関する企画提案を募集します。
-
令和7年度茨城県家庭的保育者認定研修事業業務委託に関するプロポーザルについて
-
令和7年度茨城県家庭的保育者認定研修事業業務委託に関する企画提案を募集します。
-
1月29日 茨城県の里親情報ポータルサイト「いばらき里親navi」オープン!
-
里親制度について、より多くの方に知ってもらい、社会における理解を促進させるため、里親に関する情報を包括的に提供するポータルサイトを開設しました。
-
3月16日「不妊に悩む方のおしゃべり会」を開催します!
-
ご自身の不安や疑問、治療中のストレスや想いを共有する時間を過ごしましょう。
-
第3回いばらき保育の魅力コンテストの結果発表
-
コンテスト入選施設の動画及び応募施設の取組を公開しました。
-
令和6年8月25日開催「妊活に関するオンラインセミナー」の動画を公開しました。
-
セミナー動画公開は令和6年11月30日までです。